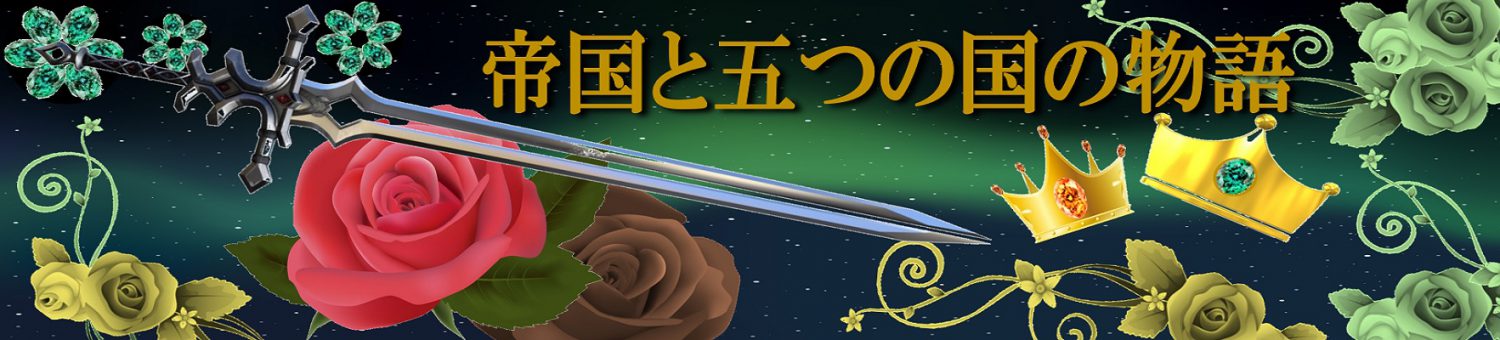リアーヌ⑳
――――――
――――
「リアーヌ、入るよ」
僅かに開けられていたとはいえ、ノックと同時に部屋に入ってきた兄を見て、私は思わず、眉尻を下げながらの苦笑を浮かべた。
「お兄様。幾ら兄妹とはいえ、今のは不躾だと思いますわ」
「え? ――――――ああ、悪かったよ。ドアが開いていたのでついね」
背後のドアを肩越しに振り返った後、反省する素振りで両手を上げて笑った兄は、確か午前中は王宮の王太子殿下の元へ出仕していた筈だ。
けれど、それに相応しい装いである灰色のジュストコールは釦が外れて既に気崩され、金髪碧眼の貴公子然とした様相が口調からしていつもより随分と砕けている。
「紳士として、今後は十分に気を付ける事にするよ。ところでリアーヌ、少し話をしたいのだが、いいかな?」
「お兄様ったら」
軽快な切り替えに、少しだけ窘めるように睨んで見せてから息を吐く。
「もちろん構いませんけれど」
「それは良かった。ちょうど庭のパビリオンにお茶の用意をさせているところだ。準備が終わったら出て来てくれ」
「まあ、パビリオンに?」
母の聖地とも呼べる建物を、兄が使おうと思いつく事が珍しい。
探るように緑玉の眼差しを見つめたけれど、数多くの女性達を躱して来た鉄壁さが私に対しても感じられて、質問を早々に諦める事にする。
「承知いたしましたわ。お兄様」
「ああ、急がなくていいからね」
片手を上げて調子よく笑った兄が背中を向けてドアを過ぎたところで、入れ替わるようにして馴染みの侍女の三人が衣装や小箱を持って入って来る。
「お嬢様、リシャール様よりお召替えをなさるようにとのご指示がございました。本日はこちらでいかがでしょう?」
「え?」
広げられた淡い青のドレスを見ると、家用ではなく明らかに迎賓用に分類されるデザインで、
「・・・どなたかお客様がいらしてるの?」
卒業を祝う夜会(ソアレ)から二日。
ジェラルド殿下とダンスを踊り、テラスで親密そうにひと時を共有した事については社交界でかなりの噂になったようだけれど、エスコートしてくれた兄も、保護者として会場にいた両親も、特に事情を訊いて来ないから私は甘えて口を閉ざしていた。
だから、もしかするとその話をしたくて兄は私を呼び出したのだと理解していたのに、どうやら違ったらしい。
ドレスに迎賓を意図する指定があるという事は、身分が上位の方をお相手するという事で、兄の友人であれば確かに公爵家の方もいるけれど、こんなにかしこまるような指示を受けた事はない。
それに、前以ってお客様についての触れが無い事も、とても訝しい気がした。
『彼は、シルベストルに忠実な男だからね』
ふと、兄に対してのジェラルド殿下の言葉を思い出して、じわりと不安が膨らんでくる。
「まさか、お客様って・・・」
ジェラルド殿下を、この屋敷にお招きになったのだろうか。
居心地の悪い戸惑いに思考を揺らしかけたところへ、侍女の一人が笑顔で口を開く。
「お客様は、公爵家のご令嬢、フランシーヌ・バジェス様でいらっしゃいますわ、お嬢様」
「フランシーヌ様?」
思いもかけなかった人物の名前に驚いた私の顔を、侍女の手によって結びを解かれた金色の髪の毛が、くるりと弾んで包み込んだ。
私が生まれ育ったデュトワ家の庭の中央にあるパビリオンは、大陸中の様々な薔薇を集めた四方の花壇を見渡す為の小さな建物で、主に母が利用している。
美しい彫刻が施された、太い柱の間から望む庭の景色はまるで絵画のようだと評判で、季節が来れば催される母の茶会はとても人気があるけれど、大きな種類の薔薇が蕾む前のこの三月は、春の色合いというよりも新緑の濃さが目立つだけの、例年はそんなパビリオンだったのに・・・、
「突然お邪魔して、申し開きもございませんわ。リアーヌ様」
パビリオンへと上る石段に足を踏み入れた時点で、兄との歓談を止めてこちらを向いたフランシーヌ様にそう切り出され、お二人の背後に咲き誇っている色とりどりの花々に目も呼吸も奪われていた私は、慌てて焦点を動かして彼女を見た。
「いいえ、フランシーヌ様。そのように改まってお言葉をいただくなんて、とんでもない事ですわ。どうかお気になさらないでください。学園でも深くお話をする機会はありませんでしたから、こうして私的な場所でお会いできて、大変嬉しく存じます」
「私も同じ思いですわ」
バジェス公爵家は、デュトワ侯爵家の主筋とは異なる上位の家柄だ。
平和な現代において、かつてのようにそれが血で血を洗う事の要因にはなり得ないけれど、それでも、多少の分別や優劣の思慮、当然の事ながら損得の答えも必要なのが貴族というもの。
学園内では、どちらかというとフランシーヌ様よりも主筋であるもう一人の公爵令嬢を立てるように行動していたから、もし彼女が本心から私との面会を希望して当家(ここ)に来たのなら、それはつまり、彼女もまた、かつての記憶を持つ者かも知れないという思考の隅で見出していた現実が、確かと実を結んでしまう。
「兄としては、色々と急すぎるのではないかと、私は一応、反対したのだがね」
どこか遠くを見るようにしながら告げた兄に、フランシーヌ様が「あら」と声に出して首を傾けた。
「そのような毅然とした態度での”反対の意”がありましたかしら? こんなに間近にいる私の、目にも耳に入らなかったなんて奇怪なお話ですわね。それとも、私の身体の調子がどこか悪いのかしら?」
「いえいえ。見る限りすこぶるお元気そうですよ、バジェス公爵令嬢。それに、反意を示されて易々と頷く貴女ではない事は知っています。私は、どこかの国の諺にあるように、ただ長い物に巻かれただけですから」
「まあ・・・、リシャール様? それは”一応反対した”という表示にはならないのではなくて? 本当に、幾つになっても、肝心な事を明確に伝えられない甘さや愚かしさは変わらないのね」
私がこれまでに見た事も気づいた事もない小さな棘を含むフランシーヌ様の口調とその様子に、対する兄は驚くでもなく、ただ震えるように目を泳がせて、苦虫を噛んだかのような表情で唇を斜めにした。
「・・・貴女のその物言いに、反射的に平伏したくなる自分が可愛いやら情けないやら・・・」
「まあ、これくらいの事で本当に情けない。ご両親が泣きましてよ」
手に持っている扇を、一羽根(ひとはね)分だけ広げたその先で唇を隠し、茶色の目を細めたるフランシーヌ様へと更に拗ねたような顔した兄は、肩を落とす。
「・・・貴女に言われたくはない」
「ふふ、そうですわね」
リシャール・デュトワ侯爵子息は、フランシーヌ・バジェス公爵令嬢に叶う事なき恋をしている。
二人のやり取りを見ている内に、私は、その噂は真相ではないのだと感じ取った。
このやり取りはまるで――――――、
「ところでリアーヌ様? ジェラルド殿下の事、お嫌いでいらっしゃるのでしょうか?」
「え?」
突然に質問を投げられた事と、その内容のあまりの単刀直入さに、私は思わず次の句を失ったまま茫然としてしまう。
「ですが、ジェラルド殿下とダンスを踊った後の貴女の顔を見た誰もが、そんな馬鹿なと否定してしまうでしょうね。――――――もちろん私も」
握り締める事によって閉じられた扇が、まるで神に誓いを捧げる時のように胸に捧げられている。
「かつて、シルベストルと呼ばれていたあの方と添い合う事が出来るのは、かつてロゼールと呼ばれていた貴女にとって、望むべき事ではあっても、意志を以って避けるべき未来では決してない筈」
ふと、焦げ茶の眼差しが、私の正面から刺すように向けられた。
「黄色のチューリップの誤解はもう解けたのでしょう? なぜ、あの方の手を取らなかったのですか?」
「フランシーヌ様・・・」
黄色のチューリップの誤解――――――シルベストル陛下は”光”と望んでくださって、私がそれを”望みなき恋”と解した事。
同時に、兄だけではなく、やはりフランシーヌ様もかつての記憶を持つ者なのだと理解してしまえば、目の前にいるこの方は一体誰なのか、とても好奇心が刺激される。
「”陛下をお慰めする事が出来るのなら、お傍に上がる事を望みたい”と、側妃になるのかと尋ねた私にあなたは確かにそう答えた。つまり、一度は強く、その覚悟を決めたのではないのですか?」
「――――――ぁ」
『ロゼール・ラフォン。あなたは、陛下の側妃として、お傍に上がる事を望みますか?』
「まさか・・・――――――ルノダ様・・・?」
驚きをそのままに呟くと、フランシーヌ様が何度かの瞬き分だけ間をおいて、その後で小さく頷いた。
当時は男性上位だったコルベールで、女性初の管理官として王宮に勤めていたルノダ様が、フランシーヌ様だなんて、
「そんな・・・」
即座に現実を受け止める事がどうしても出来ず、助けを求めるような気持ちで兄を見ると、
「私が、明確に伝えられれば良かったのだが、そういった花言葉などには私はどうも疎くて・・・すまなかった」
そんな私を、詫びで以って突き放してくる。
「お兄様・・・?」
そうなると、私の思考はますます迷うしかなく、
「陛下とロゼールの間にあったチューリップについて、前世で私が知っていたのなら、お二人のご縁が別たれる前に色々と手は打てたでしょうに、本当に、詰めのところで肝心な事が抜けているのです、貴方は」
齢十八のフランシーヌ様からは発せられるはずもない、子を窘めるような貫禄のある物言いに、兄が気まずそうに首の後ろをかく。
「もうご容赦ください。十分に反省していますから」
「いいえ。あなたは昔から反省だけは上手な子でした。政治には活かせても、色恋には終生、その反省を活かせる機会はありませんでしたが」
「・・・ですから、そのように息子の沽券を叩(はた)く様な発言はおやめ下さい、母上」
「・・・はは、うえ? ルノダ様にはご子息がいらっしゃったのですか?」
思わず口を挟んだ私に、お二人が僅かに目を開いて動きを止め、そして同時に笑い合う。
似ている筈もないのに、何故か、同じ思いを感じられるその表情は、確かに縁(えにし)を思わせる雰囲気があった。
「――――――まさか・・・」
政治に関わり、シルベストル様からロゼールに渡されたチューリップの事を知り、本人であるジェラルド殿下にすら、忠実であると言わしめる事の出来る人物は、私が知る限り一人しかいない。
「ラビヨン・・・様?」
私がぼんやりと放った呟きに、兄は真っすぐに視線を合わせたまま頷き返してきた。
その眼差しの強さには、燃えるような赤い髪をしながら、繊細に気を遣ってくださったオーブリー・ラビヨン様の人柄が偲ばれる気がする。
「薄らうすら、オーブリー・ラビヨンとして生きた記憶を戻し始めたのは2年程前からなのだよ。それまでは、私の全てはリシャール・デュトワだった。少しずつ、前世と現世が混じってきて、王太子の執務室で度々顔を合わせていたフランシーヌ嬢がかつての自分を産んだクレマンス・ルノダだと気付き、――――――とすれば、お仕えするエドワール殿下が記憶を持っていないシルベストル様かと観察してみたがどうも違う。一人で鬱々と記憶の整理を進めていた最中に、我が家の侍女の一人が母上に訴えるのを聞いたのだ。お前が修道院に行きたいなどと言い出したのは、ジェラルド殿下から黄色のチューリップが贈られてきた事が原因ではないか、殿下に弄ばれたのではないか――――――とね。同時に、その黄色のチューリップの花言葉が”望みなき恋”という事も初めて知った私は、妹であるお前がかつてのロゼール嬢である事と、ジェラルド殿下がシルベストル陛下だという事を確信し、かつてのすれ違いの真相を漸(ようや)く理解したというわけだ」
「お兄様・・・」
「さあ、これで話しやすくなったかな? かつての事情を知り、今の事情も知っている。私達は両者から見分(けんぶん)が可能な存在であると証明した。忖度なく、先ほどフランシーヌ嬢が尋ねた事について、お前自身の本当の気持ちを教えてくれるかい? リアーヌ」
ロゼールではなく、
「・・・”わたくしの気持ち”でよろしいのですか?」
刻むようにお二人に向けて問うと、肯定の意が、それぞれの眼差しから返されてきた。
それを受け止めて、私は一つ深い呼吸をしてから、意を決する。
「ジェラルド殿下の手を取れなかった理由・・・それは、――――――わたくしがこのデュトワ家に生まれ育ったという事に尽きるのだと思います」
「え?」
「リアーヌ?」
“シルベストル様が望んで下さるのなら、たとえそれがひと時の事だとしても、後宮の一室であの方をお待ちする人生を送っても構わない”
そう強く願ったロゼールは、ジェラルド殿下と添いたいと私の心の隅でひっそりと泣いている。
死の際にまで想った相手の事だから、姿は変わっても、求めたいと望むのはきっと人として当然なのかもしれない。
でも、
「わたくしには、側妃は無理ですわ」
愛妻家の父を見て育った私は、近年にコルベールで根を張り始めた”夫婦とは誠実の契りであるべき”という愛の女神《アモル》の教えを基準に、夫となる人には父と同じ程度の誠実さを求めたいと、そんな倫理を育まれてしまっている。
どんな目に遭ってもいいからと、シルベストル様の足元に縋る自分の姿が想像容易くてそれが恐ろしくて、早々に王宮を致仕したロゼールと、やはり本質は同じ。
「ジェラルド殿下はとても魅力的なお方です。ロゼールとしての切っ掛けが無かったとしても目を惹いてしまうような素敵なお方。まだ恋でもない今のまま嫁いだとしても、これから時を重ねて殿下を知る毎に、わたくしはきっと一人の女性として、あの方への愛を深めていくと思います。そして、それと同時に――――――わたくしは正妃となられる皇女を憎み、それをジェラルド様に悟られまいと己を殺して、・・・リアーヌとしても、また幸せではない人生を送ってしまう・・・」
それなら、なぜ私は生まれてきたのか。
悲しかったロゼールの二十代の人生をやり直す為ではないのか。
ロゼールとリアーヌと、一緒に幸せになるためにはどうすればいいのか。
母に解いて貰った柵(しがらみ)を忘れて冷静に思考を巡らせれば、それにはやはり、ジェラルド殿下への想いがまだぼんやりとしたものである今の内に、シルベストル様との事は”望みなき恋”であったのだと諦めて乗り越え、新しい生き方を模索した方が現世での最良ではないかと、穏やかにそう願ってしまった。
「殿下は、わたくしがどのような答えを出しても家に責めはないとおっしゃってくださいました。ですからわたくしも、貴族令嬢としてではなく、一人の女として、心のままに辞退申し上げました。――――――それが全てですわ」
言い終えて、いつの間にか伏せてしまっていた目を上げると、
「リアーヌ・・・」
「リアーヌ様・・・」
溜息を重ねたお二人が、困惑を極めた表情で真っすぐに私を見つめていた。
「お兄様・・・?」
兄の緑の目《レジュ・ヴェール》がゆっくりと動いて、背後の花々へと流れ着いた。
それを追っていた私の目も、再び、このパビリオンには珍しい花瓶に生けられた花々を捉えて映す。
「ここにある花はすべて、カーリアイネンからお戻りになられたジェラルド殿下が、以降、朝夕とお前のご機嫌伺いに贈ってきたものだよ」
「え?」
驚いたまま兄を見たけれど、直ぐに操られたように花々へと視線が戻ってしまう。
「萎れた花もあるだろうから、実際にはもっと沢山の花が贈られてきていたと思うよ」
「まさか・・・」
並べられた大小様々な花瓶の一つ一つが、その朝夕と贈られてきたそれぞれの花束なのだろう。
花の種類も色合いはどれも違っていて、ただ、どの括りにも必ずチューリップが入っているのは明らかだった。
もちろんその中には黄色のチューリップも混ざっていて・・・、
「こんなに・・・?」
胸の震えのまま、茫然と吐き出した言葉へと、応えてくれたのはフランシーヌ様だ。
「リアーヌ様。ジェラルド殿下は、薔薇の庭で再会したあのデビュタントの日から、心はずっと貴女の虜ですわ。ただ、不器用なのも、言葉が足りないのも、シルベストル様の時と比べずとも、正直、全く進歩がありませ」
「フランシーヌ嬢」
兄が口早に名を呼ぶと、「失礼」と姿勢を正して扇を広げたフランシーヌ様は、薄茶の眼差しで私を見た。
「では気を取り直して、一つ、リアーヌ様に謎かけを」
「謎かけ・・・ですか?」
「ええ」
大仰に首を縦に振ったフランシーヌ様は、隣にいる兄を見て、そして再び私へと視線を戻す。
「なぜ、デュトワ家には、ロゼール・ラフォンとオーブリー・ラビヨン、前世の記憶を持つ者が二人もいるのでしょう?」
「――――――それは・・・」
その謎に、果たして答えがあるのかどうか、私にとってはそれすらも謎で。
けれど、兄が何かを思うように口角を上げたのを見た瞬間、何かしらの法則がある事だけは理解した。
お二人の背後の花々が、風に揺れて陽の光を混ぜている。
その中で、美しいチューリップの黄色は、差す光を撥ねるように一際輝いて私には見えて、
「ジェラルド殿下に、直接お尋ねになってみてはいかがかしら?」
「・・・」
楽し気に笑うフランシーヌ様に、気が付けば導かれるようにして頷いていた。
※イチ香(カ)の書き綴った物語の著作権はイチ香(カ)にありマス。ウェブ上に公開しておりマスが、権利は放棄しておりません。詳しくは「こちら」をお読みください。